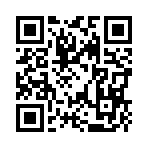腰椎分離症とは
2009年06月14日
WHO国際基準のカイロドクター at 02:17 | Comments(0) | 腰痛全般
 腰痛の種類に「腰椎分離症」というのがあります。(この写真は、背中側から見たものです。)
腰痛の種類に「腰椎分離症」というのがあります。(この写真は、背中側から見たものです。)その名のとおり、腰椎が椎弓根(赤印の部位)から分離している疾患です。
この疾患は、皮膚の上から触れただけではわかりません。レントゲン撮影などでは分離しているのが写ります。
背骨の各椎骨(一個一個の背骨のこと)は、弾性の組織で「椎間板」という線維性のクッションをを挟んで、上下の椎骨が関節を形成しています。椎骨の連結部では、内側からと外側から繋がるように関節が形成されています。
このことにより、背骨の動きが安定して機能し、思った動きが再現されます。しかし、この連結部で分離(骨折)が起きていると、背骨の動きが安定せずに思わぬ変位を招きます。
腰椎分離症での変位は、後方(背中側)に飛び出したり、前方(お腹側)に入り込んだり、さらに右回転や左回転など複数の変位を起こすことがあります。椎弓根分離により椎骨の所定の位置への安定が不可能になるため、歪み方によっては神経を圧迫して激痛を伴うケースも少なくありません。
また激痛ではないにしろ、常に痛みや違和感を感じることが多いようです。
長期にわたり、分離が酷くなるケースでは、両下肢への痛みやシビレが出たり、両足の裏にシビレ感がでたり、骨の変形が早くなったり、脊柱管狭窄症になるケースも報告されています。分離症診断の方で、長時間の座位や立位でいるとジワジワと痛みやシビレが出てくる方が多いです。
しかし、中には分離症と診断されても、全く痛みの出ない方もおられますが、姿勢を正しく管理できる環境作りと筋肉の強化をすべきです。
あまりに酷い場合は、整形で手術を要するものもあり、その場合は骨移植が行われます。そこまで行かないケースでも痛みが酷くならないように、筋力を鍛えたり、無理な姿勢に注意が必要です。特に腹筋が弱くなっていると下腹がぽっこり出てきますので、分離した椎骨が前方に滑りやすくなります。
この腰椎分離症になりやすい椎骨は、腰椎の5番(L5)と4番(L4)です。もともと腰椎全体は、若干の前彎を形成していますので、運動のし過ぎや無理な姿勢などにより分離しやすい位置にあります。
すべての人が分離を起こすわけではありませんが、子供の頃に無理な運動のしすぎにより、高校生や社会人になって違和感がより出てくる方が多いようです。痛みが取れない結果、整形でレントゲンを撮ったら、分離症診断が出たというケースも多いです。
カイロプラクティックでも、この分離症は骨折して離れている分けですから治せません。前方や後方に飛び出している場合、もしくは傾いている場合は、矯正により良い位置に戻すことは可能です。
単なる腰椎の関節の歪みであれば正しい位置に矯正し、ズレにくくなります。しかし、ストッパーになる関節が分離してしまっていますので、またズレてしまいます。これは仕方ないことなのです。
正しい姿勢の管理と体重管理、腹筋の強化が大切です。特に座する習慣のある私たち日本人は、背中が曲がりやすく、背骨も歪みやすい習慣がありますので、それまでの姿勢を変えていくことが重要です。